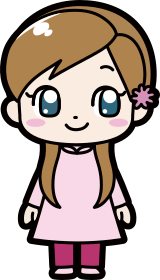
|
ベトナムのメディア 元の記事はこちら。 ( 2分で読めます ) |
乾燥したタケノコを米ぬかに浸す秘訣の科学的根拠
2025-10-31

GPT |
干しタケノコを米のとぎ汁で浸すと、毒素を除去し、シャキシャキ感と自然な風味を保つことができます。水は1日に2~3回取り替え、厚いタケノコは4~5日、薄いタケノコは2~3日、細いタケノコは5~6時間浸します。毒素のHCNを取り除くために、3~4回(15~30分)しっかりと茹でます。茹でる際は、蓋を開けて毒素を蒸発させるようにします。 |
乾燥したタケノコを米ぬかに浸すのは、古くから伝わる民間伝承です。科学的観点から見ると、この廃水にはタケノコを効果的に処理するのに役立つ多くの化合物が含まれています。
解毒サポート
米ぬかには、デンプン、ビタミンB群、タンパク質、酵素が含まれています。タケノコを浸すと、米ぬかに含まれる酵素と弱酸がタケノコを柔らかくし、シアン配糖体の分解を促します。シアン配糖体は加水分解されると、タケノコに含まれる天然毒素であるシアン化水素(HCN)を生成します。
この浸漬プロセスは、刺激臭と特有の苦味を軽減するだけでなく、毒素の除去にも役立ちます。

© vnexpress.net
シャキシャキ感と自然な風味を保つ
他の方法と比べて、米とぎ汁には独自の利点があります。塩水はタケノコを早く柔らかくするのに役立ちますが、縮みやすく、繊維質になり、歯ごたえが失われやすくなります。石灰水はタケノコ特有の風味を損ない、酢はタケノコ本来の香りをかき消してしまう可能性があります。
米ぬかは弱酸性で、セルロース繊維の構造を壊すことなく、ゆっくりと竹の子を洗い上げます。また、米ぬかに含まれるデンプン質が薄い膜を作り、酸化を防ぐため、竹の子は白く変色せず、白さを保ちます。
デンプンがわずかに発酵すると、微量の乳酸と酢酸が生成されます。これらの酸がタケノコに歯ごたえを与え、漬物のような食感を与えますが、よりマイルドな味わいになります。
損傷を防ぐ
米ぬかは乳酸菌(善玉菌)の繁殖にも適した環境です。軽く発酵すると乳酸菌が有機酸を分泌し、浸漬環境のpHを下げます。
この弱酸性の環境は、腐敗の原因となる細菌の増殖を抑制するため、塩を使わなくても、米ぬかに浸したタケノコは腐敗したり、ぬめりが生じたりしにくくなります。1日に2~3回米ぬかを交換するという伝統的な方法は、清潔な環境を維持し、強い臭いの原因となる過度の発酵を防ぐためです。

© vnexpress.net
たけのこを適切に浸す
経験上、豚タンタケノコや芽タケノコのような太いタケノコは4~5日間浸水させる必要があります。細いタケノコやタケノコは2~3日間、千切りタケノコは5~6時間浸水させる必要があります。米水は1日に2~3回交換する必要があります。
最も重要なのは、タケノコを水に浸した後、しっかりと茹でることです。これが最も重要な解毒ステップです。タケノコは何度も(少なくとも3~4回)、1回につき少なくとも15~30分茹で、きれいな水で洗い流してください。
注意:沸騰させる際は必ず蓋を開けて、HCN毒素を蒸発させてください。水が透明になり、タケノコが薄黄色になり、爪で押して柔らかくなったら、調理の準備が整います。

 vnexpress.net などで取り上げられている
vnexpress.net などで取り上げられている 



